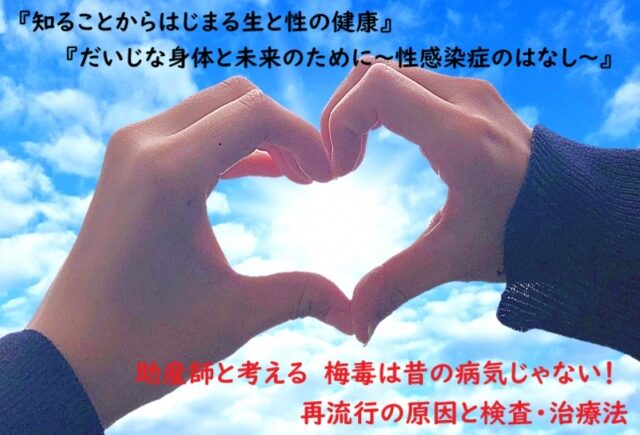「梅毒」と聞くと、昔の病気と思う方も多いかもしれません。
しかし近年、日本では梅毒の感染者が急増し、特に若い世代や妊婦さんでの報告が増えています。
症状は分かりにくく、自然に消えたように見えるため発見が遅れがちです。放置すると全身に影響を及ぼし、パートナーや赤ちゃんへの感染リスクも高まります。
本記事では、『知ることからはじまる生と性の健康』『だいじな身体と未来のために~性感染症のおはなし』~シリーズ第5回、助産師と一緒に“なぜ梅毒が再び広がっているのか”を考えながら、症状の流れや検査・治療の方法、そして妊娠・パートナー関係への影響について整理していきましょう。
梅毒はなぜ「昔の病気」と思われがち?
梅毒の原因と感染経路
梅毒は「トレポネーマ・パリダム」という細菌によって起こる性感染症です。
感染は性行為だけでなく、オーラルセックスや粘膜・皮膚の小さな傷を通じても起こります。
また、妊婦が感染している場合には胎盤を介してあかちゃんに感染し、先天梅毒の原因となります。
かつて梅毒はペニシリンの登場で激減したため「過去の病気」と思われがちですが、現在も十分に注意が必要な性感染症のひとつです。
感染は性行為だけでなく、オーラルセックスや粘膜・皮膚の小さな傷を通じても起こります。
また、妊婦が感染している場合には胎盤を介してあかちゃんに感染し、先天梅毒の原因となります。
かつて梅毒はペニシリンの登場で激減したため「過去の病気」と思われがちですが、現在も十分に注意が必要な性感染症のひとつです。
再流行している背景と社会的要因
近年、日本では梅毒の感染者が急増しており、特に20〜40代を中心に報告が増えています。
厚生労働省のデータでは、過去10年間で報告数が数倍に増加し、社会的にも大きな課題となっています。
その背景には、性感染症に関する正しい知識不足、コンドーム使用率の低下、マッチングアプリなどによる出会いの多様化があります。
また「梅毒=古い病気」という誤解から、検査や予防を軽視してしまう傾向も要因のひとつです。
助産師としては「知らなかった」では済まされない現状を伝え、世代を問わず予防の意識を高めることが大切だと感じます。
厚生労働省のデータでは、過去10年間で報告数が数倍に増加し、社会的にも大きな課題となっています。
その背景には、性感染症に関する正しい知識不足、コンドーム使用率の低下、マッチングアプリなどによる出会いの多様化があります。
また「梅毒=古い病気」という誤解から、検査や予防を軽視してしまう傾向も要因のひとつです。
助産師としては「知らなかった」では済まされない現状を伝え、世代を問わず予防の意識を高めることが大切だと感じます。
梅毒の症状と進行段階を知ろう
初期症状とその見逃しやすさ
梅毒は進行段階によって症状が変わります。
感染初期(第1期)では性器や口の粘膜にしこりや潰瘍(硬性下疳)ができますが、痛みが少ないため見逃されやすいのが特徴です。
その後、自然に症状が消えるため「治った」と勘違いしてしまう人も多くいます。
しかし菌は体内に残り、気づかぬまま次の段階へ進行します。
感染初期(第1期)では性器や口の粘膜にしこりや潰瘍(硬性下疳)ができますが、痛みが少ないため見逃されやすいのが特徴です。
その後、自然に症状が消えるため「治った」と勘違いしてしまう人も多くいます。
しかし菌は体内に残り、気づかぬまま次の段階へ進行します。
進行するとどうなる?重症化のリスク
第2期では全身に発疹(バラ疹)、リンパ節腫れ、発熱などが現れます。
これらも自然に治まることがあるため、病気を軽く考えてしまいがちです。
しかし、治療を受けずに放置すると数年〜10年以上かけて第3・4期へ進行し、心臓・血管・脳神経など全身へ深刻な障害を及ぼします。
梅毒は早期治療で完治できる一方、重症化すると命に関わることもあるため、早めの受診が重要です。
これらも自然に治まることがあるため、病気を軽く考えてしまいがちです。
しかし、治療を受けずに放置すると数年〜10年以上かけて第3・4期へ進行し、心臓・血管・脳神経など全身へ深刻な障害を及ぼします。
梅毒は早期治療で完治できる一方、重症化すると命に関わることもあるため、早めの受診が重要です。
早期発見のための検査・診断
梅毒検査の種類と受けられる場所
梅毒の診断には血液検査が用いられます。
「RPR法」「TPHA法」などにより感染の有無と活動性を確認できます。
検査は保健所や性感染症専門クリニック、婦人科、泌尿器科などで受けられます。
匿名・無料で受けられる自治体検査もあり、妊婦健診では必須項目として梅毒検査が実施されます。
臨床現場でも、妊婦健診で初めてご自身が梅毒に感染していることを知る方もおられます。
「RPR法」「TPHA法」などにより感染の有無と活動性を確認できます。
検査は保健所や性感染症専門クリニック、婦人科、泌尿器科などで受けられます。
匿名・無料で受けられる自治体検査もあり、妊婦健診では必須項目として梅毒検査が実施されます。
臨床現場でも、妊婦健診で初めてご自身が梅毒に感染していることを知る方もおられます。
検査のタイミングと注意点
梅毒は感染直後に検査しても正しい結果が出ない場合があります。
一般的には感染から2〜6週間経過してから検査すると信頼性が高いとされています。
症状がある場合は医師に相談し、必要に応じて再検査を受けることも重要です。
また、検査で陽性になった場合は、自分だけでなくパートナーも同時に検査・治療を受けることが再感染防止につながります。
一般的には感染から2〜6週間経過してから検査すると信頼性が高いとされています。
症状がある場合は医師に相談し、必要に応じて再検査を受けることも重要です。
また、検査で陽性になった場合は、自分だけでなくパートナーも同時に検査・治療を受けることが再感染防止につながります。
治療と完治までのステップ
標準的な治療法と薬について
梅毒の治療はペニシリン系抗菌薬を中心に行われます。
日本ではアモキシシリンなどの内服薬が使われ、感染時期や症状によって投与期間が決まります。
早期に治療を始めれば完治が可能であり、後遺症を残すことなく治すことができます。
ただし、抗菌薬の自己中断や不十分な治療は再発・耐性菌のリスクがあるため、必ず医師の指示通りに服薬することが大切です。
日本ではアモキシシリンなどの内服薬が使われ、感染時期や症状によって投与期間が決まります。
早期に治療を始めれば完治が可能であり、後遺症を残すことなく治すことができます。
ただし、抗菌薬の自己中断や不十分な治療は再発・耐性菌のリスクがあるため、必ず医師の指示通りに服薬することが大切です。
治療中に気をつけたい生活習慣
治療中は性行為を控えることが重要です。
症状が改善しても菌が体内に残っている可能性があるため、医師から「治癒確認」が出るまではパートナーとの接触は避けましょう。
また、規則正しい生活・十分な休養を心がけ、免疫力を保つことも治療効果を高める助けになります。
症状が改善しても菌が体内に残っている可能性があるため、医師から「治癒確認」が出るまではパートナーとの接触は避けましょう。
また、規則正しい生活・十分な休養を心がけ、免疫力を保つことも治療効果を高める助けになります。
妊娠・パートナーへの影響と地域での取り組み
妊娠中の梅毒と赤ちゃんへのリスク
妊婦が梅毒に感染していると、赤ちゃんに「先天梅毒」が起こる可能性があります。これは流産・死産、低出生体重や重度の障害をもたらす深刻な病気です。
近年、先天梅毒の報告が年間20人程度で推移していましたが、2023、2024年には年間30例を超えた報告数となり増加傾向となっています。
そのため妊婦健診での梅毒検査は必須であり、早期発見と治療によって赤ちゃんを守ることができます。
近年、先天梅毒の報告が年間20人程度で推移していましたが、2023、2024年には年間30例を超えた報告数となり増加傾向となっています。
そのため妊婦健診での梅毒検査は必須であり、早期発見と治療によって赤ちゃんを守ることができます。
パートナーと一緒に取り組む予防と、地域で学ぶ機会
梅毒は一人だけでなくパートナーの健康にも関わる病気です。
感染が分かったら隠さず、パートナーと一緒に検査・治療を受けることが大切です。
そして、コンドームの使用や定期的な性感染症検査は再感染防止に欠かせません。
助産師としては、このブログをきっかけに「自分と相手を守る性の健康」を考えるきっかけにしてほしいと思います。
また、性感染症は正しい知識を持つことが最大の予防につながります。
大阪府箕面市の「かりゆし助産院」では、園児や思春期から大人まで幅広い世代を対象に『生と性のはなし』という出前授業のご依頼をお受けしたり、今後は学びの場を計画中です。
性に関する正しい情報を安心して学べる機会を通じて、自分や大切な人の心身を守る力を育んでいきましょう。
感染が分かったら隠さず、パートナーと一緒に検査・治療を受けることが大切です。
そして、コンドームの使用や定期的な性感染症検査は再感染防止に欠かせません。
助産師としては、このブログをきっかけに「自分と相手を守る性の健康」を考えるきっかけにしてほしいと思います。
また、性感染症は正しい知識を持つことが最大の予防につながります。
大阪府箕面市の「かりゆし助産院」では、園児や思春期から大人まで幅広い世代を対象に『生と性のはなし』という出前授業のご依頼をお受けしたり、今後は学びの場を計画中です。
性に関する正しい情報を安心して学べる機会を通じて、自分や大切な人の心身を守る力を育んでいきましょう。
まとめと次回予告
梅毒は「昔の病気」ではなく、現代でも再び増えている現実があります。
感染経路や症状の特徴を正しく理解し、早期検査・治療につなげることが自分と大切な人を守る第一歩です。
妊娠中の影響やパートナーとの関わりも含め、私たち一人ひとりが考え、行動することが求められています。
かりゆし助産院では、ブログや『生と性のはなし』を通じて、地域の方々と一緒に「性と健康」について考える場を大切にしています。
そして次回は──
第6回/助産師と考える| HPVと尖圭コンジローマ:見えない感染から身を守るために
をテーマにお届けします。HPVワクチンや尖圭コンジローマの基礎知識、予防とパートナーシップについて一緒に考えていきましょう。
また、『知ることからはじまる生と性の健康』・『だいじな身体と未来のために~性感染症のはなし~』シリーズの過去ブログは下記リンクから。
感染経路や症状の特徴を正しく理解し、早期検査・治療につなげることが自分と大切な人を守る第一歩です。
妊娠中の影響やパートナーとの関わりも含め、私たち一人ひとりが考え、行動することが求められています。
かりゆし助産院では、ブログや『生と性のはなし』を通じて、地域の方々と一緒に「性と健康」について考える場を大切にしています。
そして次回は──
第6回/助産師と考える| HPVと尖圭コンジローマ:見えない感染から身を守るために
をテーマにお届けします。HPVワクチンや尖圭コンジローマの基礎知識、予防とパートナーシップについて一緒に考えていきましょう。
また、『知ることからはじまる生と性の健康』・『だいじな身体と未来のために~性感染症のはなし~』シリーズの過去ブログは下記リンクから。